国立科学博物館の年間パスポートを買ってから、こどもと3階のキッズルームのコンパスによく行っています。
コンパスの時間まで地球館を探検するのですが、
国立科学博物館のなかでも地球館は探検しがいのある場所です。
もう20回くらいは訪れていると思うのですが、
こどもがいるのでじっくりと説明をみる余裕がなく、色んな仕掛けがある地球館は今でも謎のコーナーばかりです。
そこで、今日は科博のショップで購入した「国立科学博物館のひみつ」をお昼寝のときにさっと読んでみたところ、少しだけ謎が解けました。
他のガイドマップも参考にしつつ、今日はじっくり謎を解いてみようと思います!
地球館2階 地球の映像が床に映ってる暗い部屋はなんの部屋?ていう謎
壁を床にたくさんデータが流れていますが、息子は床に腹ばいになって地球に触るのが好きです。
ガイドブックによると、
あれは、 実際に研究者が使っている世界中のデータで、現在のデータをみることができる「観測ステーション」でした。
28種類のデータがあるそうです。
なんと!見てみたいデータに手をかざすと画面が大きくなって詳細がみれるようになるしくみになっています。
知りませんでした~!
時々画面が次の表示までのカウントに変わるので、息子とカウントしながら遊んだり、息子が床に動く雲やら地形を触って寝転んでいるので、楽しそうだな、床汚いからいつ切り上げようかとか考えて過ごしていたので、壁に手を当てようとか思いつきませんでしたよ。
地球館2階 音の出る木の扉の謎
この展示室で一番おもしろそうだけど謎のものなんじゃないでしょうか(笑)
学生の頃に成績の良くなかった私は扉の文字の意味が何なのかさっぱりわかりません・・・
しっかり勉強してきた夫は「なんか微分してるな・・・」と言っていました。
1歳の息子は音がでるので誘われて近づき、
抱っこすると興味深々で扉の穴に指をつっこんで遊びます。
ガイドブックのヒントを百科辞典で調べてみました。
木の扉に書かれている式は、
電磁波の伝播を記したマクスウェルの方程式(電磁理論)でした。
この扉は、電磁場のイメージを体を動かしながら音と空間で感じるしくみだったようです。
参考 大辞林 第三版 、デジタル大辞泉 国立科学博物館のひみつ
マクスウェルの方程式 (電磁理論) って?
マクスウェルの方程式を知る前に
2人の物理学者を知っておくと面白くなると思います。
マクスウェルの方程式を知っている人は読み飛ばしてくださいね。
むかしむかし
静電気で糸がくっつくとか、磁石は鉄をくっつけるのかといった電磁現象はそれぞれ理論が存在していて、電気も磁気も別の学問として諸説ありました。
一九世紀中頃、
一人目に紹介する物理学者は鍛冶屋で生まれたファラデーさん。
書店でアルバイトしているときに独学で読書しながら科学に興味を持ち、
王立研究所教授の講演を聞いたことがきっかけで彼の助手になり、
その後、イギリスの物理学者になりました。
37年間王宮の屋根裏部屋で過ごし、
王立研究所の資金がきびしいときには毎週金曜日に講演を開き、好評だったそうです。
いくつもの実験をしながら磁気から電流が起きることを発見したり、いくつかの法則をみつけました。
二人目はイギリス北東部のエジンバラ(今は世界遺産です)という町の地主の子
マクスウェル(1831~1879)さん。
数学が得意で14歳のときに卵形曲線に関する論文を出したそうです。
(中学生で論文かあ。)
マクスウェルさんは、
ファラデーさんの法則の概念「電場、 磁場、力線」から、
4つの微分方程式にしました。
この理論から電磁波の存在が予言され、
光が電磁波であることが導かれたそうです。
それがマクスウェルの方程式。
現在の電磁気学の基礎になっています。
「力線」といえば・・・
地球館の地下3階に目で見える実験装置があります!
あれかあ。と少しつながった気がする。
ちなみに、E は電場,H は磁場,D は電束密度,B は磁束密度,i は電流密度,ρは電荷密度,t は時間を表わすそうです。
なぜマクスウェルの方程式なのか?
おそらく、私の考えですが
マクスウェル方程式がいろんな電磁現象を説明できる電磁気学の基礎だから。
なんで国立科学博物館の地球館で電磁気学のエリアを作ったのかというと、
宇宙のことや自然のしくみを調べるために電気磁気学が重要な分野だからです。
電磁気学は、力学とともに、自然科学すべての基礎をなしている。
日本大百科全書
「ピ~」って音の謎
木の扉に書いてある式の謎は解けたけど、
あの扉に近づいたり離れたりすると「ピ~」って音が大きくなったり小さくなったりします。
あれは何かという謎。
購入した本を読んだら、「あの音はテルミンです。」と書いてありました。
テルミンってなんですか(笑)
また式ですか!?
テルミンってなに?
アンテナに手を近づけたり遠ざけたりすることによって、音の高低と音量を加減して演奏する。世界最古の電子楽器として知られる。
大辞林 第三版
電子楽器だったんですね。
空間を音で感じるには良い楽器のチョイスです!
ちなみに、テルミンはアンテナが2つあるそうです。
音の高い低いと、大きさを調整するアンテナ。
木の扉のアンテナはどこなのか?
「 国立科学博物館のひみつ」に載っていた写真には扉のノブがあって、
なんかそれっぽいです。
もう一つはどこだろう?
なぞが少し残っていますが・・・
次回行った時に探してみよ~^^
長くなったので、今日は一旦ここまで!
また更新します!
追記 テルミンのアンテナを調べてみた
今日、地球館の2階にまた行ってきました。
マクスウェルの方程式の扉の、
音の出るところを探してみました。
中央の覗き穴の下にある2つの穴がアンテナだと思います。
追記2 マクスウェルの方程式の扉の近くにファラデーも近くにいた
ちなみに、
マクスウェルの方程式の扉の目の前にある水の円盤には、ファラデーさんの実験の説明がさらっとあります。
私はマクスウェルの方程式のことを調べた後で気づいたので、
「こんなところにファラデーさんのことが書いてある!」と新しい発見をして面白かったです。

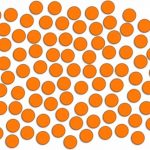




コメントを残す